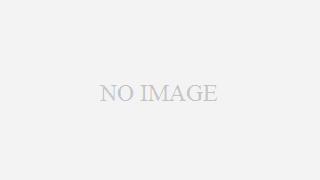 文学
文学 11. 平凡 1
四、「平凡」
「平凡」は四迷が「其面影」迄の研究で獲得した思想を、当時最盛期を迎えていた自然主義に対する批判として展開した作品である。自然主義の批判者として日本のリアリズムの創始者である四迷ほどの適任者はいなかったしその後も「平凡」を越える自然主義批判は現れなかった。
四迷はこの作品についても結局サタイヤになってしまい失敗だと言っている(1)。四迷の意図と違った形式になった点でも、批判が十分には展開されなかった点でも「失敗」であった。批評がこの言葉を手掛かりに見苦しい小理屈をこねているのは言うまでもないが見苦しさの紹介はしない。我々は四迷の基準からすれば失敗であったこの作品が日本文学史の発展上果たした役割を分析し、「浮雲」や「其面影」を描いた厳しい精神だけが実現できる自由で軽妙なサタイヤを楽しむことにしよう。自然主義作家の思想と行動は悲劇として観察するにはレベルが低すぎる。四迷も自然主義作家を、下らぬことを大げさに書さ散らすだけの無能な文士と考えていた。彼らの悩みは主観的に深刻であるほど滑稽になる。だから本来サタイヤがふさわしい。
『平凡』かね。いや失敗して了ったよ。...