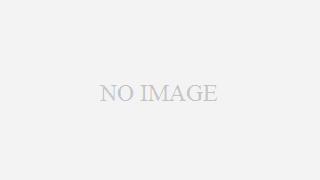 文学
文学 17. 彼岸過迄 1
「作の性質だの、作物に対する自己の見識だの主張だのは今述べる必要を認めてゐない。実をいふと自分は自然派の作家でもなければ象徴派の作家でもない。近頃しば々々耳にするネオ浪漫派の作家では猶更ない。自分は是等の主義を高く標榜して路傍の人の注意を惹く程に、自分の作物が固定した色に染附けられてゐるといふ自信を持ち得ぬものである。又そんな自信を不必要とするものである。・・・
東京大阪を通じて計算すると、吾朝日新聞の購読者は実に何十万といふ多数に上つてゐる。其の内で自分の作物を読んでくれる人は何人あるか知らないが、其の何人かの大部分は恐らく文壇の裏通りも露路も覗いた経験はあるまい。全くたゞの人間として大自然の空気を真率に呼吸しつゝ穏当に生息してゐる丈だらうと思ふ。自分は是等の教育ある且尋常なる士人の前にわが作物を公にし得る自分を幸福と信じてゐる。」
この「彼岸過迄に就て」には「門」にたどりついた漱石の力が感じられる。漱石は抽象的な主義主張で述べることができないほど具体的で豊富な内容を描写する能力を蓄積した。漱石はこれまでの作品の系列の帰結としてこの作品の社会的位置を強く意識して 「面白いもの...